屋根塗装の後に雨漏りが起きる理由とその防止策
2025.08.28
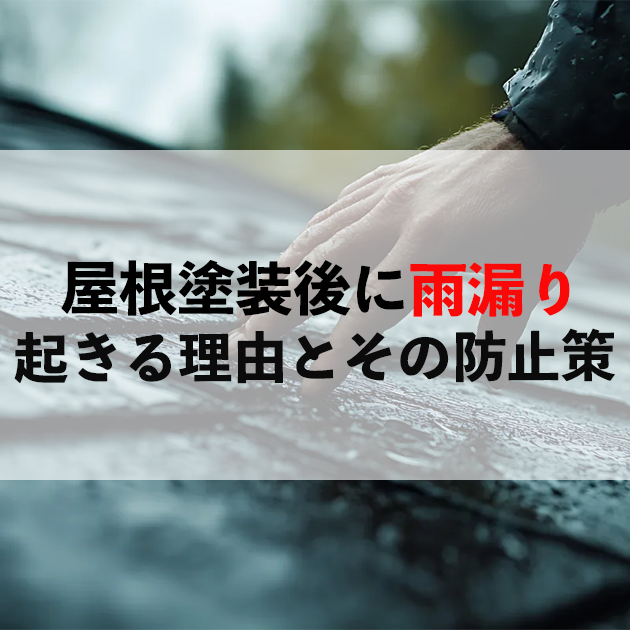
いつも塗るばいブログをご覧いただきありがとうございます!塗るばいは佐賀を中心に、地域密着型の外壁塗装専門店として、外壁塗装、屋根塗装、屋根カバー工法、屋根葺き替え、防水工事、雨漏り修理など、幅広いサービスを提供しています。当店では高品質な塗装を手頃な価格でご提供し、お客様の住まいをより長持ちさせるお手伝いをしています。
「屋根塗装をしたのに、まさかの雨漏り…?」そんな悩みに共感します
戸建て住宅の屋根塗装後に、突然の雨漏りに悩まされるケースが少なくありません。実際に「屋根塗装 雨漏り」というキーワードで検索される方が増えており、不安に感じている方が多い証拠です。
この記事では、「なぜ屋根塗装の後に雨漏りが発生してしまうのか」「雨漏りの主な原因とは何か」「再発を防ぐための具体的な防止策」について、塗装業者視点の体験談も交えながら解説します。
1.屋根塗装後に雨漏りが起きる主な原因

1-1 施工不良と不具合:職人の技術で結果が変わる
屋根塗装後の雨漏りは、施工ミスによるものが非常に多いです。
屋根塗装後に雨漏りが起きたという相談の中でも、最も多く寄せられる原因のひとつが「施工不良」です。見た目は綺麗に塗られていても、細部の処理や技術力に問題があると、雨水の侵入を防げず、結果として室内に雨漏りが発生してしまいます。
とくに多いミスは以下の3つです。
-
縁切り不足
スレート屋根の塗装で、塗料が屋根材同士の隙間を塞ぎ、水の逃げ道がなくなってしまうケースです。これが原因で雨水が逆流し、屋根内部に水が浸入する「毛細管現象」が発生します。 -
コーキング施工のミス
コーキング(シーリング)材を誤って塗ってしまう、または古いコーキングを撤去せずにその上から塗ってしまうと、隙間が残って防水機能が失われます。 -
高圧洗浄の不備
屋根表面の汚れや苔を十分に落とさずに塗装をすると、塗膜の密着が悪くなり、剥がれやひび割れが生じて雨漏りに直結します。
体験談:
私たちが担当したお客様の中で、「3ヶ月前に別の業者で屋根塗装を行ったが、突然の豪雨で雨漏りが始まった」と連絡を受けたケースがありました。屋根を点検したところ、スレートの隙間がすべて塗料で密閉されており、タスペーサー(縁切り用の器具)が全く使われていませんでした。施工の丁寧さや技術力の違いが、こうしたトラブルに直結します。
対策:
-
信頼できる施工実績のある業者に依頼すること。必ず「屋根塗装 雨漏り」対策の経験が豊富な専門業者を選びましょう。
-
工事中に写真を撮ってもらうよう依頼すること。特に縁切り処理、下地処理、高圧洗浄の様子など、見えない工程こそ記録しておくことが重要です。
-
工事保証の有無を確認すること。最低でも5年以上の保証がある業者は信頼度が高い傾向にあります。
1-2 劣化した下地の影響:見た目では分からない構造的な問題
塗装工事はあくまで表面の処理であり、屋根の内部構造には手を加えません。
「屋根塗装をしたのに雨漏りが止まらない」というケースでは、屋根の下地に深刻な劣化があることが多いです。屋根塗装は基本的に表面の保護や見た目の美化を目的としており、防水機能の根幹を担う「ルーフィング」や「野地板」には直接アプローチできないのです。
築年数が15年以上経過した戸建て住宅では、屋根材の内部にある下地が湿気や雨水により腐食していることが少なくありません。特に多い劣化ポイントは以下の通りです:
-
防水シート(ルーフィング)の寿命
防水シートの耐用年数は約15〜20年。表面に問題がなくても内部では劣化が進み、雨漏りの原因になります。 -
野地板の腐食やカビ
屋根材の下にある野地板が湿気を吸って腐り、釘が抜ける・板がずれると、雨水の侵入口になってしまいます。 -
屋根裏の結露・湿気による構造劣化
換気が不十分だと屋根裏に湿気が溜まり、構造材まで影響が出ます。
体験談:
以前、築20年以上のお宅で屋根塗装だけを希望されたお客様に調査を実施したところ、釘が浮いていたり、野地板が腐食して一部崩れ落ちている状態でした。表面の塗装を行っても意味がないため、「部分的な葺き替え」をご提案しました。その結果、屋根の耐久性も上がり、以降の雨漏りは一切発生していません。
対策:
-
屋根塗装の前に、ドローンや目視、打診による屋根診断を必ず行うこと
-
必要に応じて「カバー工法(重ね葺き)」や「屋根葺き替え工事」を検討する
-
業者に「劣化状況の写真」や「下地の確認報告書」の提出を依頼する
屋根塗装だけで全てを解決しようとすると、見えない構造劣化に気付けず、雨漏りリスクを抱えたままになってしまいます。屋根の「内側」にも目を向けた判断が重要です。
1-3 毛細管現象による浸入:雨水が逆流する落とし穴
結論:塗装後の雨漏り原因の中で、最も見落とされがちなのが「毛細管現象」です。
毛細管現象とは、狭い隙間に水が逆流し、本来なら排出されるはずの雨水が屋根内部に侵入してしまう現象です。スレート屋根など、重なり合った屋根材を塗装する際、塗料が隙間を完全にふさいでしまうことで、雨水がスムーズに流れなくなり、隙間を通って内部に吸い込まれてしまいます。
この現象は、次のような施工不備で起こります:
-
タスペーサー未使用
-
縁切り処理の未実施
-
通気や排水ルートを意識しない塗装設計
見た目は綺麗でも、「雨水の動線」が確保されていないと、水がどこにも逃げられず、屋根材の裏側に水が滞留します。それが内部に染み込み、雨漏りの原因となってしまいます。
体験談:
あるお客様は、屋根塗装後わずか2週間で雨漏りが発生しました。点検したところ、スレート屋根が塗料で完全にふさがれており、タスペーサーも一切使われていませんでした。縁切り処理を後から実施し、水の通り道を作ることで、症状はピタリと止まりました。
対策:
-
スレート屋根には必ずタスペーサーを使用する
雨水の排出経路を確保するためには、縁切り専用部材であるタスペーサーが不可欠です。 -
塗装前後に水の流れを確認する
雨樋の詰まりや、勾配が適切かも合わせて確認しましょう。 -
必要に応じて散水試験を行い、施工不良がないか検証する
施工後すぐに問題を発見できれば、保証内での対応が可能です。
毛細管現象は「きちんと塗装したはずなのに雨漏りが起きる」典型的な原因です。屋根塗装 雨漏りのリスクを避けるには、こうした現象を理解した上で、施工プランを立てることが重要です。
▼合わせて読みたい▼
2.無料の屋根点検サービスを上手に活用して雨漏りのリスクを事前に回避しよう

2-1 塗装業者による無料点検サービスを利用することで得られる具体的なメリット
屋根塗装を検討する際には、信頼できる塗装業者による無料点検サービスを受けることが極めて重要です。
この点検により、屋根材の劣化、塗膜の剥がれ、コーキングの割れ、雨樋の不具合など、目視だけでは把握できない劣化状況を事前に把握できます。
特に以下のようなメリットがあります:
-
雨漏りの原因となる箇所を塗装前に発見できる
-
下地や構造部分の劣化が進んでいないかを判断できる
-
部分補修や葺き替えの必要性を早期に検討できる
-
施工の優先順位や予算の最適化ができる
屋根は常に風雨や紫外線にさらされており、築10年以上の住宅では見た目以上に劣化が進行していることがあります。無料点検は、後悔しない塗装工事の第一歩です。
2-2 点検の際に必ず確認すべき質問事項の具体的チェックリストとその目的
無料点検を受ける際には、塗装業者に任せきりにせず、施主自身も質問や確認をする姿勢が重要です。
下記のような質問を点検時に行うことで、施工後の雨漏りリスクを効果的に抑えられます。
| 質問内容 | 目的・意図 |
|---|---|
| 屋根の下地(野地板・ルーフィング)の劣化状況はどうか? | 表面の塗装だけでなく、構造的な問題がないかを確認する |
| タスペーサーの使用予定はあるか? | スレート屋根の場合、毛細管現象による水の逆流を防ぐため必須 |
| 高圧洗浄はどの程度行うか? | 汚れが残ると塗膜の密着不良で早期劣化を招く |
| コーキングの打ち替えは全面実施か? | 劣化部分だけでなく、すべてのコーキングを補修するかを確認 |
| 施工中の写真記録をもらえるか? | 工事の透明性を高め、後からのトラブル回避に有効 |
このように、「見えない部分こそ事前に確認する」姿勢がトラブル防止につながります。
2-3 屋根塗装のあとに雨漏りが発生する代表的な原因とその効果的な予防方法
スレート屋根塗装で発生しやすい毛細管現象が引き起こす雨水の逆流とその防止策
スレート屋根を塗装する際に縁切り作業を行わないと、毛細管現象によって雨水が屋根材の裏へ逆流してしまうことがあります。
この現象は、塗料が隙間を埋めてしまうことで水の逃げ道がなくなり、逆に雨水が吸い上げられて屋内へ侵入してしまう現象です。
【予防方法】
-
スレート屋根には必ずタスペーサーを使用する
-
縁切り作業の有無を契約時に確認する
-
施工後に散水テストを実施して異常がないかを確認する
特に築15年以上経過した屋根では、劣化したスレート同士が密着しやすく、毛細管現象が発生しやすくなります。
見た目だけでは気付かない屋根下地の劣化が原因で発生する構造的な雨漏りリスク
屋根塗装はあくまで表面の保護作業であり、下地材や構造部分の補強は含まれていません。
そのため、野地板の腐食、防水シートの破れ、釘の浮きといった内部劣化が進行していると、塗装後すぐに雨漏りが発生する可能性があります。
3.屋根塗装のあとに雨漏りが起きたときの正しい応急処置と早期対応の重要性

3-1 雨漏りを発見したときにすぐにできる具体的な応急処置の方法と注意点を詳しく解説
屋根塗装の直後に雨漏りが発生した場合は、まず落ち着いて応急処置を行うことが重要です。以下は、家庭でできる初期対応の基本です。
【応急処置の手順】
-
水の受け皿を設置する
雨漏り箇所の下にバケツや洗面器を置いて、床や家具の被害を防ぐ。 -
天井や壁紙にビニールシートをかぶせる
水が広がらないよう、被害の範囲を限定する。 -
周囲の電化製品の電源をオフにする
感電やショートを防ぐため、漏電ブレーカーを落とすことも有効。 -
水のしみ出し範囲を記録・撮影する
後日の調査や補償交渉のため、写真や動画で記録しておくと安心。
【注意すべき点】
-
自力で屋根に登るのは非常に危険。雨天時は絶対に避けること。
-
濡れた天井を突いて水を抜く処置は、専門知識がなければ構造を傷める恐れがある。
-
漏れてくる水が茶色や黒い場合は、木材の腐食やカビが進行している可能性がある。
このような一次的な処置を行うことで、二次被害(家電の故障、床の腐食、カビの発生など)を防ぎつつ、冷静な修理対応に進めます。
3-2 雨漏り発生後は迅速な修理依頼が建物へのダメージを最小限に抑える鍵となる理由
応急処置を施したら、できる限り早く屋根塗装業者または雨漏り修理の専門業者に連絡を取ることが必須です。
なぜなら、雨漏りは時間の経過とともに建物構造全体へ深刻なダメージを与える可能性が高いからです。
【雨漏りを放置した場合のリスク】
| リスク内容 | 具体的な影響 |
|---|---|
| 木部の腐食 | 野地板・垂木が腐り、屋根がたわんだり沈下したりする |
| カビの発生 | 天井裏や壁内部でカビが繁殖し、健康被害の原因に |
| 電気配線のショート | 雨水が配線に触れると漏電・火災リスクが高まる |
| 断熱材の劣化 | 濡れた断熱材が機能せず、室内温度が安定しない |
【迅速な修理のポイント】
-
施工した塗装業者へ優先して連絡し、保証範囲を確認する
-
屋根材の破損・浮き・ひび割れの有無をチェックしてもらう
-
必要に応じて第三者の雨漏り調査専門業者を呼んで二重チェックを行う
-
火災保険の補償対象になるかも確認する(風災や水害の場合)
屋根塗装の直後であれば、保証期間内で無償修理となるケースが多いため、すぐに業者へ報告することが最も効果的な対応です。
3-3 屋根塗装後の雨漏りは「業者の施工不良」が原因かを見極めるための判断基準とは
雨漏りが発生した場合、まず疑うべきは「屋根塗装工事の施工ミス」です。
すべての雨漏りが施工不良ではありませんが、発生時期と原因箇所によっては施工業者の責任が明確になるケースがあります。
【施工不良が疑われるパターン】
| 状況 | 可能性のある施工不良 |
|---|---|
| 塗装から数日以内に雨漏り発生 | タスペーサー未使用・縁切り不足による毛細管現象 |
| 雨漏り箇所が塗装範囲と一致 | 板金部の隙間処理不備、コーキング不良 |
| 強風・台風などの要因なし | 自然災害でなければ施工側の瑕疵の可能性が高い |
【判断基準と対応の流れ】
-
施工時の報告書・写真・契約書を確認し、作業内容を整理
-
業者の現地調査を依頼し、原因特定と責任範囲を説明してもらう
-
第三者機関や保険会社に相談することで、公平な判断を得られる
-
業者に瑕疵担保責任の有無を確認し、修理・賠償請求の準備を進める
屋根塗装業者が「保証付き工事」を行っているかどうかも、大きな判断材料になります。信頼できる業者であれば、責任を持って迅速に対応し、今後の対策も提案してくれます。
まとめ
屋根塗装の後に雨漏りが発生する原因には、「縁切り不足」「コーキングの劣化」「板金の隙間処理の不備」など、施工上の問題が関係しているケースが少なくありません。
また、経年劣化や下地の腐食、予期せぬ自然災害など、塗装前に潜んでいたリスクが顕在化することもあります。
だからこそ、屋根塗装を依頼する際には、事前の点検の質と、信頼できる業者選びが非常に重要になります。
施工前には屋根材の状態を正確に診断し、必要であれば補修や交換も視野に入れること。
施工後には保証の有無を確認し、万が一の際の対応力も業者選定の判断基準としましょう。
「屋根塗装 雨漏り」は、トラブルとしては深刻ですが、原因と対策を正しく理解することで十分に防ぐことができます。
この記事を通じて、雨漏りへの不安が軽減され、安心して屋根塗装工事に臨めるようになれば幸いです。
塗るばいでは、佐賀でお客様にピッタリの塗装プランを提案しています。佐賀の外壁塗装、屋根塗装、防水工事は塗るばいにお任せください!!
私が担当しました!

営業
國分 大輔Kokubu Daisuke
誠心誠意ご対応させていただき、お客様がご満足いただける工事を行えるよう尽力いたします。よろしくお願い致します。
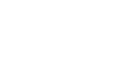


 お問い合わせ
お問い合わせ

