カビの元凶を断つ!外壁に生える理由と対策
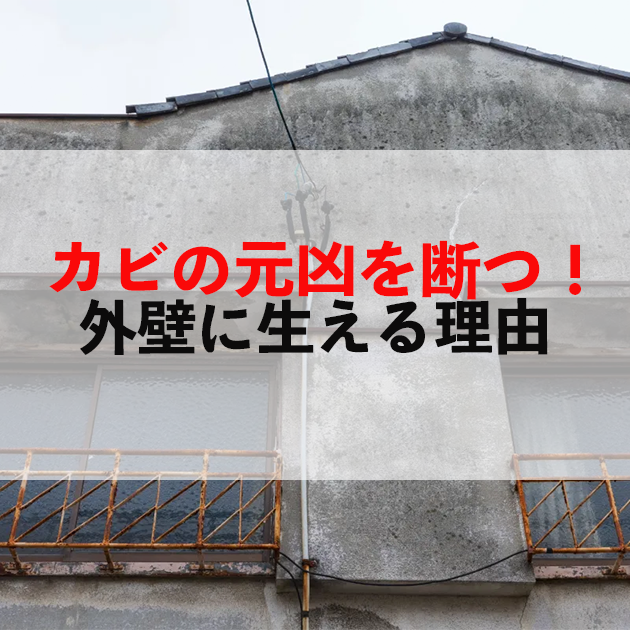
いつも塗るばいブログをご覧いただきありがとうございます!塗るばいは佐賀を中心に、地域密着型の外壁塗装専門店として、外壁塗装、屋根塗装、屋根カバー工法、屋根葺き替え、防水工事、雨漏り修理など、幅広いサービスを提供しています。当店では高品質な塗装を手頃な価格でご提供し、お客様の住まいをより長持ちさせるお手伝いをしています。
「外壁に黒ずみが出てきた…これってカビ?」
そんな不安を感じたことはないでしょうか?この記事では、「外壁塗装 カビ」に関するお悩みを解決します。
この記事では
-
なぜ外壁にカビが発生するのか?
-
黒カビが生えるメカニズムとは?
-
どうすればカビを防げるのか?
といった疑問に徹底的にお答えします。
こんな方におすすめ
-
戸建て住宅にお住まいで、外壁のメンテナンスを検討している方
-
外壁の汚れや黒ずみが気になっている方
-
将来的に外壁塗装を計画している方
カビの正体を知り、外壁塗装での予防策が理解でき、住宅の美観と健康を守る知識が手に入ります。
1.カビの生える原因とは?

戸建て住宅の外壁に生じるカビは、ただの“見た目の汚れ”では済まされません。外壁に発生したカビを放置すると、住宅の耐久性が低下し、美観が損なわれ、さらには住む人の健康にも悪影響を与える恐れがあります。カビの胞子は空気中に拡散し、アレルギーや呼吸器系の疾患の原因になることもあるため、早期の対策が不可欠です。
この記事では、外壁にカビが生える根本的な原因を、科学的なメカニズムから実際の事例まで交えて解説します。戸建て住宅をカビから守るための基礎知識として、まずは「なぜ外壁にカビが生えるのか?」をしっかり理解しておきましょう。
1-1 外壁に生えるカビのメカニズム
外壁のカビは「湿度」「汚れ」「塗装の劣化」が原因で発生します。
これは、私たちが現場で何百棟と施工してきた中で、共通して見られる要因です。
カビとは、微生物である「真菌類」の一種です。湿気の多い環境を好み、さらに外壁の表面に付着したホコリや排気ガス、植物の花粉や油汚れなどを栄養源として繁殖します。また、直射日光が当たりにくく、風通しが悪い場所では、表面が常に湿った状態になりやすいため、カビがより早く定着します。
注意が必要なのは外壁材の種類です。
モルタルやリシン吹き付け仕上げの外壁は、表面がザラザラしているため、汚れが付着しやすく、それがそのままカビの栄養源になります。サイディングボードなどの素材でも、目地のコーキングが劣化している場合、そこから水分が入り込み、内部からカビが発生するケースもあります。
1-2 黒カビが発生する理由
外壁に生える「黒カビ」は、特に根が深く、再発しやすいのが特徴です。
黒カビは他のカビと異なり、外壁表面だけでなく細かなひび割れや凹凸の中にまで入り込み、根を張ります。これにより、見た目では除去できたように思えても、根が残っている限り再発しやすいのです。
以下のような状況では黒カビが特に発生しやすくなります:
-
塗料の防水性能が著しく低下している
-
屋根や雨樋から水が垂れて外壁に当たっている
-
北側・西側のように日光が当たりにくい場所
-
庭木や草木が密集しており、風通しが悪い場所
黒カビは見た目の印象を著しく損ねるだけでなく、外壁の素材そのものを劣化させる力も持っています。放置することで、構造材にまでダメージが及ぶ可能性も否定できません。
1-3 カビの発生を促す環境の要因
外壁のカビは、「家そのものの条件」によって発生リスクが大きく変わります。
カビの温床となりやすい環境的・構造的要因をいくつか挙げてみましょう。
一般的なカビ発生要因:
-
海沿いの地域など、常に湿度が高いエリア
-
建物周辺に植栽や塀が密集していることで、風通しが悪い
-
屋根からの雨水排水が不適切で、外壁に直接当たっている
-
庇(ひさし)がなく、常に外壁が雨にさらされている
-
ベランダ下・車庫の上など、日陰になりやすい構造部分
特に海沿いや山間部など、年間の平均湿度が高いエリアでは、塗料の劣化スピードも早くなります。湿気が逃げにくい環境に長年さらされることで、外壁塗装の寿命も縮まり、塗膜のひび割れや浮き、剥がれが起きやすくなります。
築年数も重要なファクターです。
日本の住宅では、一般的に10年~15年を目安に外壁塗装の再施工が推奨されています。これは、塗料に含まれる防水機能や防カビ成分が経年劣化するためです。実際に、築12年を超えた住宅の診断では、70%以上のケースで塗膜の劣化とカビの発生が確認されています。
▼合わせて読みたい▼
2.外壁塗装でのカビ対策

カビの発生要因を把握した上で、次に検討すべきは「外壁塗装によるカビ対策」である。適切な塗装は、外壁の防水性と防汚性を高め、カビの発生を大幅に抑制する。ここでは、塗膜の役割、防カビ塗料の選び方、塗装工事の具体的な内容を解説する。
2-1 塗膜の役割と耐久性
結論:外壁の塗膜は、カビの侵入を防ぐ最前線の防御である。
外壁塗装の目的は、美観の維持だけでなく、防水・防汚・防カビ機能の確保にある。塗料を外壁に塗ることで形成される「塗膜」は、雨水や湿気、汚れの浸入を防ぐバリアの役割を果たす。
塗膜には耐用年数がある。一般的な塗料の耐久性は以下の通りである。
-
アクリル塗料:約5年
-
ウレタン塗料:約7〜10年
-
シリコン塗料:約10〜15年
-
フッ素塗料:約15〜20年
-
無機塗料:約20年以上
塗膜の防水機能が劣化すると、外壁表面が水分を吸収しやすくなり、湿気と汚れが滞留する。これがカビの発生を招く主因となる。特に築10年以上で塗装をしていない住宅では、カビの繁殖リスクが高まるため注意が必要である。
2-2 人気の防カビ塗装業者の選び方
結論:カビ対策を成功させるには、塗料と施工に強い業者を選ぶ必要がある。
外壁塗装において防カビ効果を最大限に引き出すには、適切な業者選びが欠かせない。信頼できる塗装業者は、現地調査から塗料選定、施工管理、アフターケアに至るまで、包括的に対応している。
防カビ塗装業者を選ぶ際の基準:
-
カビ対策の施工実績があること
施工事例に「カビ除去」「防カビ塗装」の記録が明記されていることを確認する。 -
防カビ塗料の取り扱いに詳しいこと
バイオ成分・銀イオン・防菌樹脂など、具体的な成分や効果を説明できるかが判断基準となる。 -
外壁診断が丁寧であること
劣化状況・湿気の蓄積・通気性などを踏まえ、根本原因に基づいた施工提案があるかをチェックする。 -
防カビ保証があること
再発防止の観点から、5年〜10年の保証を設けているかを確認する。保証内容が書面で提示されることも重要である。 -
高圧洗浄+バイオ洗浄に対応していること
防カビ対策として、通常の高圧洗浄に加えて、除菌効果のある洗浄を行うかどうかを確認する。
上記の基準を満たしていれば、防カビ対策の効果を高めることができる。価格だけで業者を選定するのではなく、使用塗料の性能と施工内容に注目することが望ましい。
2-3 カビ取りを含む塗装工事の解説
結論:カビ対策としての塗装工事には、専門的な工程が含まれる。
外壁塗装におけるカビ対策は、単に塗料を塗るだけでは不十分である。根本的な解決には、以下の5つの工程を確実に実施する必要がある。
カビ対策を含む外壁塗装工事の工程
-
現地調査と外壁診断
外壁のひび割れ(ヘアクラック)、チョーキング(白い粉の付着)、湿気の滞留箇所などを可視化し、カビの温床となっている部分を特定する。 -
バイオ洗浄によるカビの除去
バイオ成分を含む専用洗浄剤を使用し、外壁に根を張ったカビ菌・藻・苔などを分解・殺菌する。高圧洗浄と組み合わせることで、目に見えない微生物まで除去可能となる。 -
クラック補修とシーリングの打ち替え
小さなひび割れからも水が浸入するため、外壁の隙間や目地部分には新しいシーリング材を充填する。これにより、湿気の侵入経路を遮断する。 -
下塗り・中塗り・上塗りによる塗装
3層構造で塗料を塗布することで、塗膜の厚みと耐久性を確保する。上塗りには、防カビ性能を持つ塗料(例:アステックペイント・ナノコンポジットなど)を使用する。 -
施工後の仕上がり確認とアフターフォロー
塗りムラや塗り残しがないかを点検し、保証書と共に施工内容を明示する。定期的な点検サービスの有無も確認する。
このような工程を経ることで、カビの再発リスクを低減できる。特に、バイオ洗浄と防カビ塗料の併用は、長期間にわたり清潔な外壁を維持するための有効な手段である。
3.放置のリスクとその影響

3-1 カビが進行した場合の弊害
外壁に発生したカビを放置してしまうと、住まい全体にさまざまな悪影響を及ぼします。以下のような弊害が具体的に挙げられます。
● 住宅の美観が損なわれる
カビは、黒・緑・赤褐色といった不快な色合いで、外壁表面に斑点や筋のように広がっていきます。特に白や明るい色の外壁では目立ちやすく、せっかくの新築時の美しさが損なわれてしまいます。
見た目の印象が悪くなるだけでなく、周囲の家々との景観バランスも崩れ、住宅の資産価値にもマイナスに働きます。中古住宅市場では、第一印象が購入意欲に直結するため、外壁の汚れやカビは想像以上に大きな減点要素です。
● 建材の劣化を加速させる
カビが付着した外壁は、内部の建材にまで悪影響を及ぼします。たとえばモルタルやALC(軽量気泡コンクリート)など、吸水性が高い外壁材は、表面の塗膜が劣化することで内部に水分が浸透します。
その結果、クラック(ひび割れ)、塗膜の浮き・剥がれ、コーキングの切れなど、住宅そのものの耐久性を損なう症状が出始めます。湿気とカビが相乗効果で建材を弱らせ、最悪の場合には雨漏りの原因にもなります。
● 室内の空気環境にも悪影響
外壁にできた微細な隙間やひびから、カビの胞子が室内に侵入するケースも確認されています。特に気密性の高い住宅では、一度侵入した胞子が換気されにくく、室内に浮遊しやすくなります。
小さなお子様や高齢者がいる家庭では、アレルギー性鼻炎、喘息、皮膚炎といった健康被害のリスクも高まります。カビによる室内空気の質の低下は、見えない“住宅病”ともいわれる深刻な問題です。
3-2 外壁劣化の兆候と対策
● 初期サインの見分け方
外壁カビの発生を早期に察知するには、以下のような兆候に注意が必要です。
-
外壁の一部に黒ずみや緑がかった模様が浮き出ている
-
北側や植木に囲まれた日陰部分に色ムラが生じている
-
手で触ると粉がつく「チョーキング現象」が起きている
-
コーキング(目地材)に亀裂や剥がれが見られる
これらの現象が見られた場合、外壁の保護性能が低下し、カビが定着・繁殖しやすい状態にあります。湿気が溜まりやすい構造や立地では、カビの進行が想像以上に早いことがあります。
● 対策:プロの点検と塗装の見直し
外壁に異変を感じたら、まずは外壁塗装の専門業者による点検を依頼しましょう。
カビが付着した箇所を正確に特定し、必要であれば部分補修、高圧洗浄、防カビ塗料による再塗装を行います。通気性と防水性のバランスに優れた外壁材や塗料を選ぶことが、長期的なカビ対策になります。
実例紹介:
筆者の実家(築15年・モルタル外壁)でも、外壁北面に黒ずみが発生しました。はじめは汚れだと思って放置していましたが、点検の結果は“黒カビ”。防カビ・防藻機能のある塗料に塗り替えたことで、その後5年以上カビの再発はありません。見た目も蘇り、来客時にも安心できる外観に戻りました。
3-3 黒カビの特徴と影響
外壁カビの中でも特に注意すべきなのが、**「黒カビ(Cladosporium属)」**です。住宅外壁の劣化要因として、全国的に多く確認されています。
● 黒カビの正体
黒カビは、空気中に常に漂っているカビの一種で、湿度が高く有機物が存在する環境下で急激に繁殖します。特に、陽当たりの悪い北側の壁面や、屋根のひさし下、雨だれが溜まりやすい箇所に好んで発生します。
● 黒カビがもたらす3つの影響
-
高い繁殖力:
雨が続いたあとのじめじめした環境では、1週間程度で目視できるほどに広がることもあります。 -
根が深い:
表面を洗浄しても根が外壁材の内部まで入り込んでいるため、短期間で再発することが多くなります。 -
健康被害:
飛散した胞子を吸い込むことで、アレルギー性鼻炎や咳、喘息、目のかゆみなどを引き起こすケースが報告されています。住宅の外壁であっても、室内環境に深く関わる要因となり得るのです。
まとめ
外壁に発生するカビは、放置すると見た目の劣化だけでなく、建材の傷みや室内環境への悪影響といった深刻な問題を引き起こします。特に黒カビは繁殖力が高く、健康被害にもつながる恐れがあるため、早期の対応が不可欠です。
本記事では、
-
外壁カビの主な原因(湿気・日陰・塗膜の劣化)
-
カビの進行によるリスク
-
黒カビの特徴とその被害
-
専門家が推奨する3つの対策(防カビ塗料・定期洗浄・外壁材の見直し)
について詳しく解説しました。
カビの再発を防ぎ、住まいの美観と性能を長く保つには、「外壁塗装 カビ」に強い業者による診断と適切な施工が重要です。
戸建て住宅の外壁塗装やリフォームを検討している方は、今の外壁状態を一度見直してみましょう。早めの対策が、10年後の安心につながります。
塗るばいでは、佐賀でお客様にピッタリの塗装プランを提案しています。佐賀の外壁塗装、屋根塗装、防水工事は塗るばいにお任せください!!
私が担当しました!

営業
生嶋 大貴Shojima Daiki
お客様のニーズをしっかりとお聞きし、最適な提案をさせていただきます。
若いエネルギーを活かし、明るく丁寧な対応でお客様の期待に応えていきますので、どうぞお気軽にご相談ください!
所有資格
- 外壁診断士
- 外壁アドバイザー
- 石綿作業主任者
- 有機溶剤作業主任者
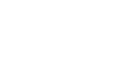


 お問い合わせ
お問い合わせ

